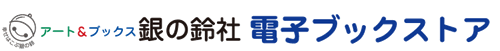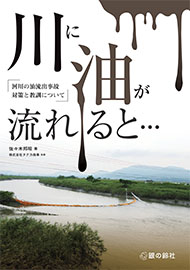川に油が流れると・・・―河川の油流出事故対策と教訓について―
概要:
川に油が流れた時、一刻を争う適切な対処が必要になります。
先人が経験して得た教訓をもとに、一緒に考えてみてください。
今からでも遅くない と願って・・・
本書出版進行中に次々と起こった油流出事故。
日本にある数万の大小の河川。そのどこかで、ある日突然発生する、未経験で想定外の事故。
身近な河川での突然の事故に、「今からでも遅くない防災の術」を伝えたい!
油流出事故の対策に世界中で経験を積んできた著者の、渾身の1冊。
はじめに
1960年代、石油を大量に消費する時代になるとともに、油が海洋に流出する事故が頻発するようになった。その件数は海上保安庁の白書によると数万件に及び、特に、大型タンカー等が座礁や衝突事故を起こすと流出油の規模が大きく、国際的な問題となった。川のように流れる油の帯、海浜を埋め尽くす油塊、涙し怒る人々、油にまみれた自然や鳥等の姿、その様な映像が幾度も世界中に伝えられた。
そして流出油対策の国際条約(1954年 OIL POL条約、1973年MARPOL73/78条約等)が締結された。日本は条約の国内法化を行うとともに対策を強化してきた。その成果もあって、近年海洋の油濁事故は著しく減少した。
一方、陸域でも油濁事故は多発し、国土交通省の統計には今日数万件が記録されている。工場、ホテル、学校、事業所、寄宿舎、役所、一般家庭そして農家のビニールハウス等で使われる重油や灯油等が、配管の損傷、器械の故障、交通事故等様々な原因により排水路を経由して川へ流出する事故は、毎年1,000件以上のペースで発生している。その多くが揮発性のある油種で小規模とはいえ想定外の被害を伴うことも少なくなかった。
私は海上災害防止センターに昭和59年から21年間勤務し、海の油濁対応に数多く取り組んでいた。平成18年に現役を引退した後も今日まで「漁場油濁基金」の専門家として、又は NPO「川の油濁防止技術研究会」の要員として要請があった時、油が流れる海と川の現場に赴き支援してきた。これらの経験から、河川では海洋のレベル程にはハードやソフトが整備されていない(程遠い)事を強く感じている。
その理由は、日本には国際河川(複数の国家の領土を流れる川)がない、欧米で発生している様な大規模(数百~数千klの流出)の河川油濁事故もない、河川の管理者の在任期間が短く専門家が育たない、他の河川での経験が共有されていない等によると思っている。
川に油が流出する事故は、大量の油が使われ輸送される限り、これからも様々な形で発生し続けるため、最新の知見を備えた対応能力をもつ責任者の存在は不可欠である。対応が拙ければ公共への被害が拡大してしまうからである。
日本には数万の大小の河川があり、その何処かである日突然、未経験で想定外の事故がこれからも必ず発生するはずである。
その前提のもとに、現場対応の人材を確保することは必要なことである。本書でとりあげるイロハを知れば油濁対応は過剰に恐れることなく、立ち向かう事ができる。
佐々木邦昭
目次:
◆もくじ◆
第1章 河川と水質事故
1、川の区分 2、河川の油濁による被害と対策 3、一級河川の水質事故 4、一級河川以外の油流出事故について 5、水質事故と関係法令について 6、河川・内陸油濁の特徴
第2章 水質事故対応
1、油の性状を把握 2、情報伝達の確認 3、河川油濁への対応 4、集油の必要性 5、油で汚染された土砂の扱いについて
第3章 資機材とその運用
1、オイルフェンス(OF) 2、簡易堰 3、油吸着材 4、回収装置 5、薬剤
第4章 事例調査
事例調査
資料編
資料1、関係法文 関係する法規と条文
資料2、海外の河川油濁事故(北米) 北米で発生している河川の流出油事故
資料3、海外の河川油濁事故(北米以外) 北米以外で発生している河川の流出油事故
- ジャンル:
- 経済 > 産業・交通 社会・政治 > 社会問題 教育 > 教育一般
販売(無期限): ¥ 660(税込) / ギフト購入: ¥660 (税込)